9月3日(まえがき)
ベジファーストがなぜ良いのかを徹底的に調べた。単なる「野菜から食べる」以上の意味があることがわかってきて、食材の種類や食べ方、さらには野菜がないときの対応策まで掘り下げた一日。
ベジファーストの本質は「繊維ファースト」
ベジファーストと呼ばれる習慣の科学的な核は、野菜そのものではなく食物繊維の作用。特に水溶性食物繊維は胃でゲル状になり、糖や脂質の吸収速度を遅らせる。これによって血糖値の急上昇を防ぎ、インスリン分泌を穏やかにする。
さらに、消化管ホルモンGLP-1やPYYの分泌が促されることで、食欲抑制やインスリン感受性改善に寄与する。つまり、順番を変えるだけで代謝に直接影響を与えている。
実際に効果的な食材
普段の食卓にある10品
キャベツ、レタス、ブロッコリー、ほうれん草、きゅうり、トマト、大根、もやし、なめこ、わかめ。
これらは比較的安価で手に入りやすく、血糖抑制効果や抗酸化作用が確認されている。特に葉物・海藻・きのこは臨床研究でも有効性が示されており、ベジファーストの軸として外せない。
野菜がなくても代用できる食材
海苔、乾燥わかめ、素焼きナッツ、納豆、枝豆、インスタント味噌汁(わかめ・なめこ入り)。
重要なのは「食物繊維か良質な脂質を先に摂る」ことであって、野菜というカテゴリにこだわる必要はない。
効果を高める食べ方
時間の工夫
野菜を食べたらすぐ主食に進んでも効果はある。ただし、5〜10分かけて食べ進め、その後に炭水化物へ移行するほうが血糖曲線はさらに安定する。30分以上置くと逆に空腹感が強まり、効果が減る。
量の目安
食物繊維として5g以上、野菜なら100〜150gが目安。両手に軽くのる程度のサラダ、あるいは味噌汁+小鉢一品で十分。食べすぎると消化不良やガスのリスクもあるため、バランスが大事。
落とし穴と注意点
- ドレッシングの糖分:ノンオイルや甘いタイプは砂糖多め。オリーブオイル+酢でシンプルに。
- 根菜やジュース:にんじん、かぼちゃ、じゃがいもは糖質が高め。ジュースは繊維が取り除かれ血糖スパイクを招く。
- 揚げ物野菜:天ぷらや油炒めはカロリーと脂質で台無し。蒸すか軽く茹でるのが理想。
- 食べるスピード:一気食いでは効果が減る。先に5分をかけて野菜類を食べるのがポイント。
一皿料理のときの戦略
カレーや丼物など、最初から混ざった料理はベジファーストが難しい。そういうときは以下で対応できる。
- 前に海苔やナッツを数口食べてから主食に入る
- カレー自体を繊維リッチにする(ブロッコリー、ほうれん草、きのこを追加)
- 食後に10分歩くことで血糖をさらに安定させる
副菜ゼロの状況でも「小さな前置きアイテム」を仕込んでおけば切り抜けられる。
今日の観測まとめ
ベジファーストは単なる「野菜から食べる習慣」ではなく、食物繊維やホルモン制御を通じた代謝介入の方法。最適解は「野菜100〜150gを5〜10分かけて先に食べ、その後に主菜・主食」。副菜がなくても、海苔やナッツ、もずくパックといった代替手段で十分対応できる。
食事という日常的行為の中に、科学的な工夫と実践可能な戦略を組み込むことで、自分の体調や血糖カーブをデザインできる。その発見を今日の観測ログとして残しておく。
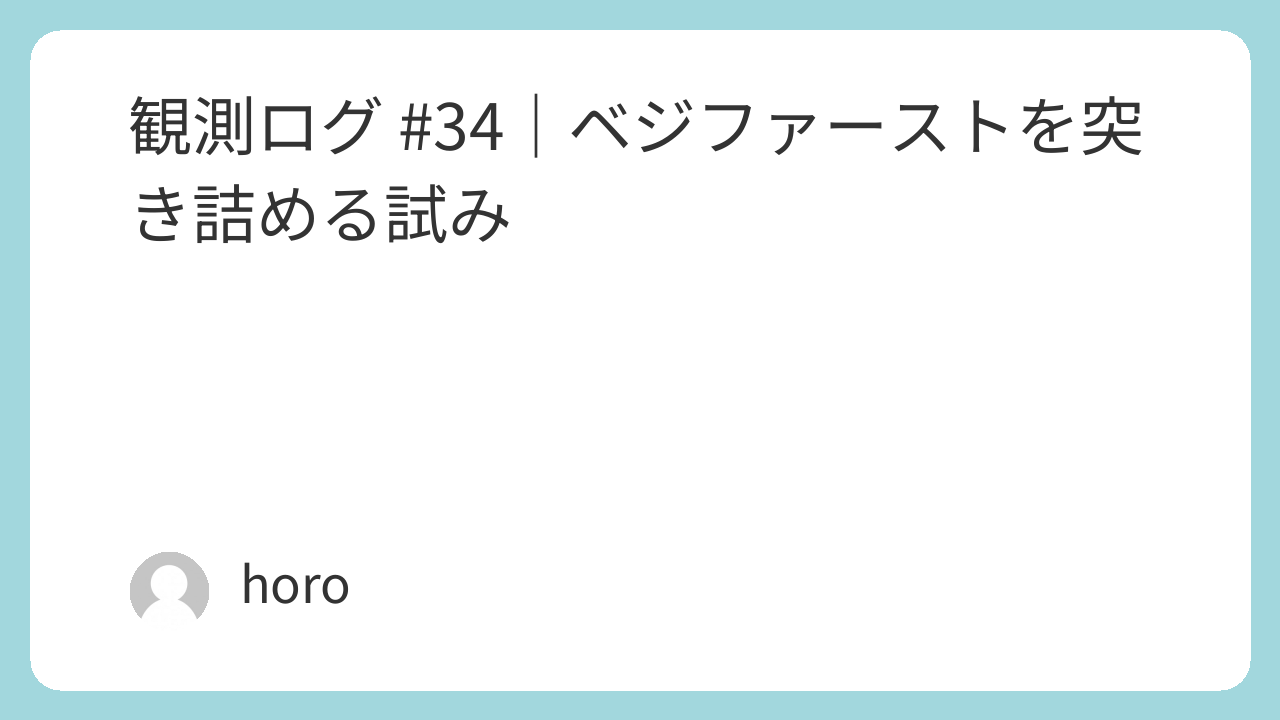
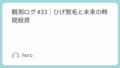
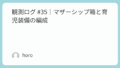
コメント